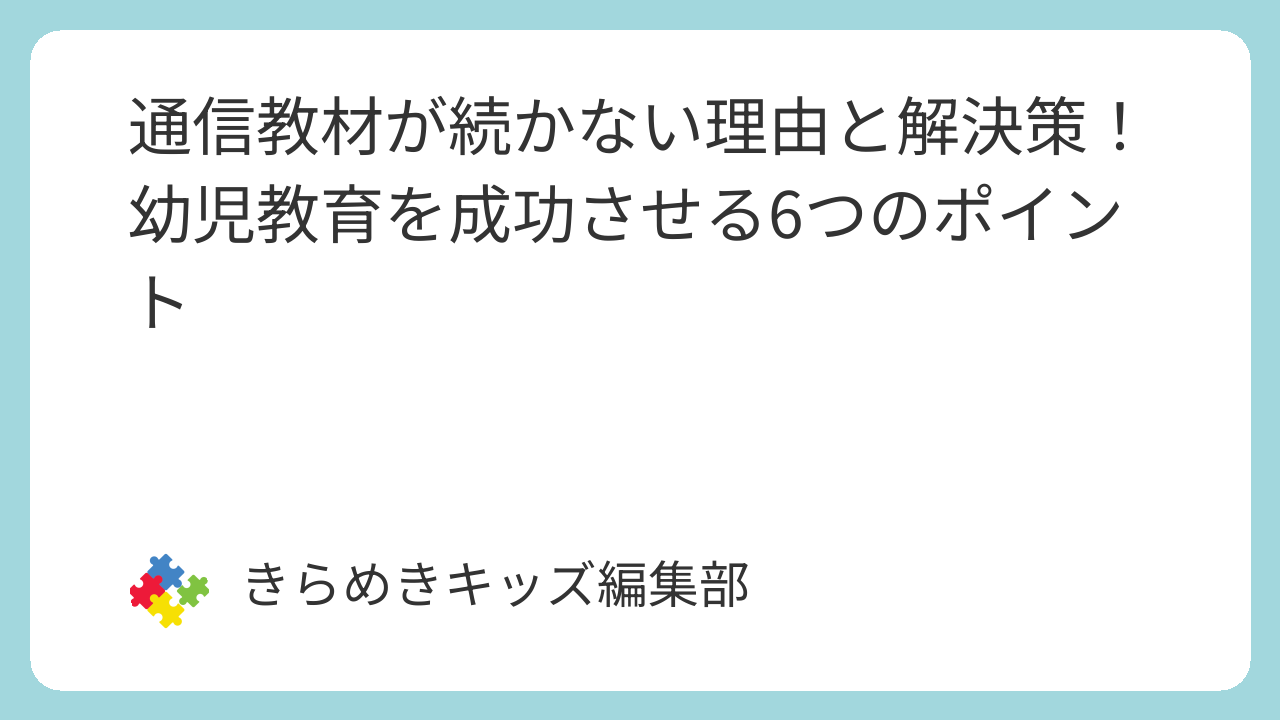「せっかく通信教材を始めたのに、子どもが飽きてしまって続かない…」
そんな悩みを抱えているご家庭は実は多いのです。約4割の小学生が利用するという通信教育ですが、実際その効果は?という声が聞かれるように、始めるのは簡単でも継続は難しいのが現実です。
でも大丈夫。通信教材が続かない原因を正しく理解し、適切な対策を講じれば、お子さまが楽しく学習を続けられるようになります。編集部では実際に3人の子どもを育てる中で、さまざまな通信教材を試してきた経験から、続けるためのコツをお伝えします。
通信教材が続かない3つの主な理由
1. 教材の難易度が子どもに合っていない
レベルが合わないと、どんなに良い通信教育でも効果を発揮しません。これは通信教材選びで最も重要なポイントです。
難しすぎる場合の症状
- 問題を見ただけで嫌がる
- わからないことが多く、すぐに諦める
- 親に頻繁に助けを求める
簡単すぎる場合の症状
- すぐに終わってしまい、つまらないと感じる
- 適当に答えを書いてしまう
- 新しい学びや達成感が得られない
2. 学習環境が整っていない
いつも遊んでいる場所とは別に学習スペースを設けると、勉強のスイッチが切り替わりやすいです。
子どもが集中できる環境作りは、継続のための重要な要素です。テレビがついている、おもちゃが散らかっている、家族が騒がしいといった環境では、どんなに良い教材でも効果は期待できません。
3. 親のサポートが不足している
幼児が通信教材を進めるには、親のサポートが必要です。1人で勉強することに不安を感じる子どももいるので、その場合は親が横で見守ってあげることで安心して取り組めます。
特に幼児期においては、一人で学習を進めることは困難です。親の適切なサポートがあることで、子どもは安心して学習に取り組むことができます。
年齢別:通信教材が続かない特有の理由
2-3歳の場合
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 集中力が短い(3-5分程度) | 短時間で区切る・一緒に取り組む |
| 言葉での説明が理解できない | 実際に手を動かして見せる |
| 興味の対象がコロコロ変わる | 複数の教材を用意・子どもの興味に合わせる |
4-5歳の場合
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 他の遊びの方が魅力的 | 学習も「遊び」として位置づける |
| できないことへの挫折感 | 小さな成功体験を積み重ねる |
| 自分でやりたい気持ちが強い | 一人でできる部分と親がサポートする部分を明確にする |
6歳の場合
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 学校の勉強との内容のズレ | 学校の進度に合った教材選び |
| 友達との遊び時間を優先したい | 学習時間を明確に設定・メリハリをつける |
| プライドが高く、間違いを嫌がる | 間違いは成長のチャンスだと伝える |
通信教材を続けるための6つの解決策
1. 子どもに合った教材選びの基準を明確にする
教材選びのチェックポイント
✓ 子どもの現在の発達段階に合っているか ✓ 興味のある分野や好きなキャラクターが含まれているか ✓ 1回の学習時間が子どもの集中力に適しているか ✓ 親のサポートがどの程度必要か明示されているか
編集部の田中さんは、「うちの子は絵を描くことが大好きだったので、アート要素の多い教材を選んだところ、3年間継続できました」と話しています。
2. 学習環境を整える3つのステップ
Step1: 専用スペースの確保
- テーブルの上を片付ける
- 学習道具を手の届く場所に配置
- テレビや音楽を消す
Step2: 時間の固定化 毎日決まった時間になったら同じ場所に座って遊ぶなどからはじめ、少しずつ習慣づけしていくとよさそうです。
Step3: 家族の協力体制作り
- 学習時間中は静かに過ごす
- 兄弟姉妹も一緒に机に向かう
- テレビやスマホの使用を控える
3. 親のサポート方法を段階的に調整する
初期段階(開始~1ヶ月)
- 隣に座って一緒に取り組む
- 読み上げや指差しでサポート
- できたことをすぐに褒める
中期段階(1-3ヶ月)
- 近くで見守りながら、必要な時だけサポート
- 子どもからの質問に答える
- 週単位でできたことを振り返る
安定期(3ヶ月以降)
- 一人でできる部分を増やす
- 困った時のサインを決める
- 学習の記録を一緒につける
4. モチベーション維持の仕組み作り
小さな達成感を積み重ねる
「頑張ってもどうせ認めてもらえない」となれば、通信教材を続けるモチベーションもなくなっていくでしょう。当たり前に続けていることこそ、「毎日取り組めているね」などと努力を認めてあげることがモチベーションの維持につながります。
効果的な褒め方の例
- 「今日も机に向かえたね」(行動を褒める)
- 「最後まで頑張ったね」(継続を褒める)
- 「昨日よりも早くできたね」(成長を褒める)
5. 「続かない」を「続ける」に変える習慣化のコツ
21日間ルールの活用
幼児期に身につけた習慣は、生きていく上でおこなうことが「当たり前」として受け入れられやすくなります。
習慣化のための具体的なステップ:
第1週(1-7日目)
- とにかく毎日机に向かうことを最優先
- 内容や時間は気にしない
- できたらシールを貼る
第2週(8-14日目)
- 決まった時間に取り組むことを意識
- 簡単な内容から始める
- 「昨日もできたね」と継続を認める
第3週(15-21日目)
- 学習内容を少しずつ充実させる
- 子ども自身に「今日はやった?」と確認させる
- 習慣になりつつあることを伝える
6. 教材変更のタイミングと方法
変更を検討すべきサイン
- 2週間以上連続で嫌がる
- 親が無理やりやらせている状況が続く
- 子どもの学習レベルと明らかに合わない
続かない理由が難しいという場合は、躊躇なくコースを変更したり、通信教育自体を変更することをおすすめします。
編集部おすすめ:続けやすい通信教材の特徴
継続しやすい教材には共通の特徴があります:
特徴1: 段階的な難易度設計
- 子どもの発達に合わせた細かなレベル分け
- 無理なく次のステップに進める構成
- 復習機能が充実している
特徴2: 親へのサポートが充実
- 取り組み方の指導書が詳しい
- 子どもの反応に応じたアドバイス
- 困った時の相談窓口がある
特徴3: 飽きさせない工夫
- 季節やイベントに合わせた内容
- ゲーム要素の適度な組み込み
- キャラクターとの親しみやすさ
よくある質問と解決法
Q: 教材が溜まってしまいます。どうしたらいいですか?
A: まず溜まった分は一旦片付けて、今月分だけに集中しましょう。やりたいと言った子どもの最初の気持ちだけに任せていては、続けるのは難しいのです。溜まってしまった状況を見るとプレッシャーになってしまいます。
Q: 他の習い事と両立できません。
A: 通信教材の大きなメリットは時間の自由度です。通信教育は時間に縛りがありません。お子さまの気分に合わせたり、スキマ時間を利用して取り組むことができるため、保護者も子供もお互いに負担が少なく、続けやすいというメリットがあります。平日は10分、休日は30分など、メリハリをつけて取り組みましょう。
Q: 子どもが全く興味を示しません。
A: まずは教材を「勉強」として位置づけず、「遊び」として提示してみてください。また、取り組むのはお子さん自身。自分からお子さんが進んで取り組めることが、一番子どもの成長に役立つんですよ。子どもの興味のある分野から入ることが重要です。
継続のための具体的なタイムスケジュール例
平日の場合(30分コース)
| 時間 | 活動内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 16:00 | 帰宅・おやつ | リラックスタイム |
| 16:30 | 学習準備 | 子どもと一緒に机を片付ける |
| 16:35-17:05 | 通信教材 | 30分集中・親は近くで見守り |
| 17:05 | 片付け・振り返り | 「今日もがんばったね」 |
休日の場合(45分コース)
| 時間 | 活動内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 10:00 | 朝の準備完了 | 生活リズムを整える |
| 10:30-11:15 | 通信教材 | 平日より少し長めに設定 |
| 11:15 | 自由時間 | やり終えた達成感を味わう |
まとめ:通信教材を続けるために最も大切なこと
通信教材が続かない理由は様々ですが、最も大切なことは「子どもに合った教材選び」と「適切な環境作り」、そして「親の継続的なサポート」です。
学習習慣の定着は、長い目で見ると子ども自身の強い武器となります。頑張って学習習慣が定着する環境を保護者が作ってあげてください。
無理をせず、お子さまのペースに合わせながら、小さな成功体験を積み重ねることで、必ず継続できるようになります。もし今使っている教材が合わないと感じたら、迷わず他の教材を検討することも大切です。
編集部からのアドバイスとして、「完璧を求めすぎない」ことをお勧めします。毎日できなくても、週に4-5日できれば十分です。お子さまと一緒に楽しみながら、学習習慣を身につけていきましょう。
通信教材は、使い方次第で子どもの可能性を大きく広げてくれる素晴らしいツールです。この記事が、皆様の幼児教育の成功につながることを心から願っています。