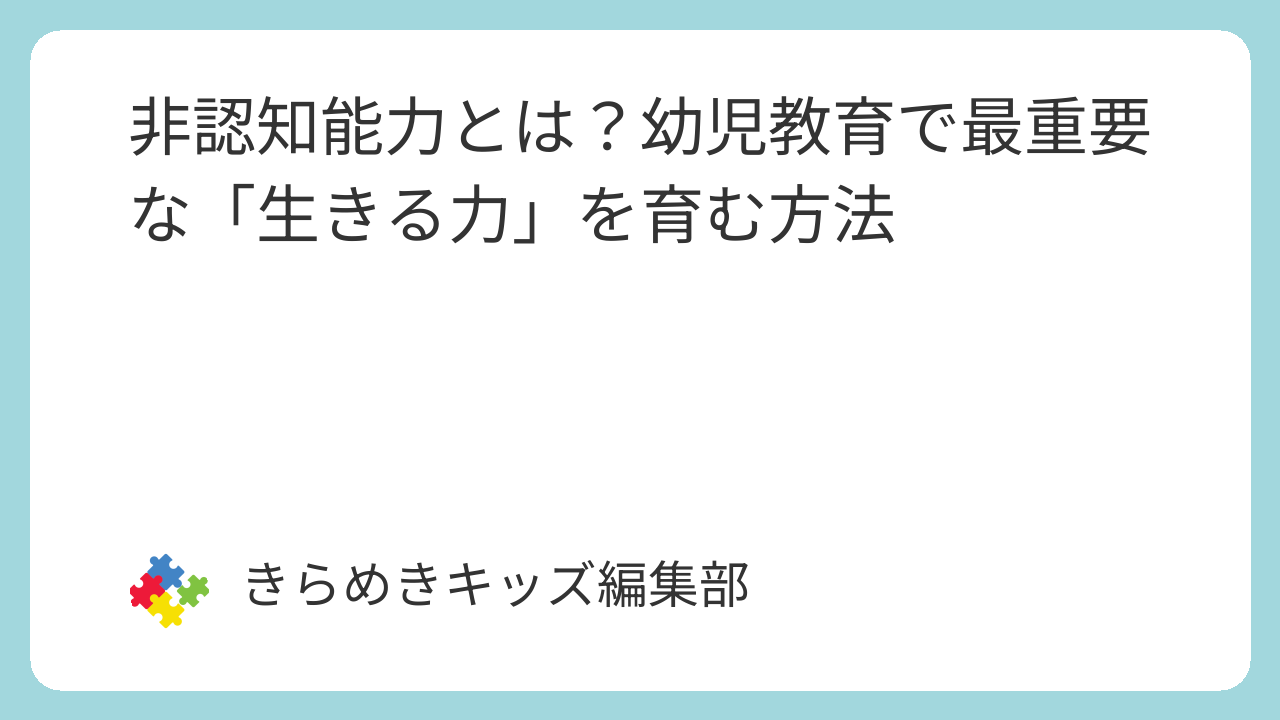子どもの将来を考えるとき、「どんな力を身につけさせてあげればいいのだろう」と悩まれるご夫婦は多いのではないでしょうか。近年、教育界で注目を集めているのが「非認知能力」という概念です。これは、単純にテストの点数や偏差値では測れない、人生を豊かに生きるための根本的な力を指します。
非認知能力とは何か?基本的な理解
非認知能力とは、IQや学力テスト、偏差値などのように点数や指標などで明確に認知できるものではないけど、子どもの将来や人生を豊かにする一連の能力のことです。具体的には、以下のような力が含まれます。
非認知能力の主な要素
| 分野 | 具体的な能力 |
|---|---|
| 自己に関わる力 | 自尊心、自己肯定感、忍耐力、意欲、自制心 |
| 社会性に関わる力 | 協調性、思いやり、コミュニケーション能力、共感力 |
| 目標達成に関わる力 | やり抜く力、計画性、創造性、柔軟性 |
多岐にわたる非認知能力は、大きくふたつに分けられます。ひとつめは「自己に関わる心の力」。これは、自分を大切にし、感情を適度にコントロールでき、自己を高めようとする力のことで、自尊心や自信、自己肯定感、「きっとできる」と思える自己効力感などがあります。ふたつめが「社会性に関わる心の力」。ほかの人を信頼し、うまくやっていくための力で、協調性や思いやりなど、いわゆる社会性ともいわれるものです。
認知能力との違い
認知能力と非認知能力の違いを理解することは重要です。
認知能力と非認知能力の比較
| 項目 | 認知能力 | 非認知能力 |
|---|---|---|
| 測定方法 | IQテスト、学力テストで数値化可能 | 数値では測定困難 |
| 具体例 | 読み書き、計算、記憶、推論 | 意欲、忍耐力、協調性、自制心 |
| 育成方法 | 反復練習、暗記などが中心 | 体験、人との関わりが中心 |
| 発達時期 | 学習を通じて段階的に向上 | 幼児期に基礎が形成される |
私たち編集部でも実際に子育てを経験する中で、「算数ができる」ことと「困難にめげずに頑張る」ことは全く別の力だということを実感しています。例えば、我が子が積み木で思うような形が作れずに泣いてしまったとき、その場で諦めるのではなく、何度でもチャレンジする姿勢を見せた時の成長は、単純にテストの点数よりもずっと価値のあるものだと感じました。
非認知能力が注目される理由
科学的根拠:ペリー就学前プロジェクト
非認知能力が世界的に注目されるきっかけとなったのが、アメリカのシカゴ大学の経済学者であり2000年にノーベル経済学賞を受賞し、『幼児教育の経済学』の著者のジェームズヘックマン氏の研究です。
ペリー・プレスクール・プロジェクト(Perry Preschool Study)とは、1962年から1967年にかけてアメリカで行われた就学前教育の社会実験。現在でも被験者の追跡調査が行われている。
この研究では、質の高い幼児教育を受けたグループと受けなかったグループを40年以上にわたって追跡調査した結果、教育を受けたグループに以下のような効果が見られました。
ペリー就学前プロジェクトの主な結果
| 項目 | 教育ありグループ | 教育なしグループ |
|---|---|---|
| 高校卒業率 | 77% | 60% |
| 月収2000ドル以上の割合 | 42% | 26% |
| 持ち家率 | 37% | 28% |
| 生活保護受給率 | 59% | 80% |
| 逮捕歴のある割合 | 55% | 69% |
興味深いことに、幼児教育プログラムを受けた子ども達のIQや学力テストは一時的に上昇しましたが、8歳前後では受けていない子ども達と大きな差がなくなったという点も重要です。この実験では、IQに代表される認知能力の上昇はできたけれど、効果は持続しなかったのです。
しかし、研究者が心理学的な方法で数値化したところ、プログラムを受けた子ども達の「非認知能力」が育っていたことが分析されています。
現代社会での重要性
現在、世界はいわゆる”VUCA”な時代の直中に在ると言われています。”VUCA”とは、Volatility(激動)、Uncertainty(不確実)、Complexity(複雑)、Ambiguity(曖昧)という4つの英単語の頭文字を並べてつくられたことばです。
このような激変する社会において、子どもたちには以下のような力がより一層求められています:
- 予期せぬ変化に対応する柔軟性
- 困難な状況でも諦めない忍耐力
- 多様な人々と協働する力
- 自分の感情をコントロールする力
編集部のスタッフの一人は、コロナ禍でのリモートワークを経験する中で、「自分で計画を立てて実行する力」や「孤独感に負けない精神力」がいかに重要かを実感したと話していました。これらはまさに非認知能力の要素そのものです。
文部科学省における非認知能力の位置づけ
日本の教育政策においても、非認知能力は重要視されています。文部科学省は小学校教育につながる幼児期の学びの特性として、非認知能力を主に3つの観点からまとめています。①自分の目標を目指して粘り強く取り組む ②そのためにやり方を調整し、工夫する ③友達と同じ目標に向けて協力し合う
幼稚園教育要領での位置づけ
2018年度幼稚園教育要項では『第2節 幼稚園教育において育みたい資質・能力及び幼児期の終わりまでに育ってほしい力 45項〜』の中で非認知能力に値する「学びに向かう力、人間性等」が重要な柱として位置づけられています。
これは従来の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」と並ぶ第三の柱として設定されており、日本の教育においても非認知能力の育成が国家的な重要課題となっていることがわかります。
非認知能力を育む具体的な方法
1. 遊びを通じた育成
子どもの興味が次々と新しいものに移る時は、気持ちの向くままに好きなことをさせてあげましょう。「目移りしないで、ひとつのことに集中してほしい」と感じることもあるかもしれませんが、もしかするとその遊びの中で、想像力や創造力など”何か別の力”が育まれているかもしれません。非認知能力とは、実に多岐にわたるもの。子どもの意思を尊重し、自由に取り組ませてあげる中で、さざまな力が自然と育まれていくものです。
2. 応答的な関わり
幼児教育における「質の高さ」に、「応答的な人的環境」が挙げられます。子どもが目の前の花を「あっ」と指差せば、周囲の大人が「お花が咲いてるね、きれいね」と応える。これが応答です。なんでもないように思えますが、ここには自分の興味に対し、一緒に目を向けてもらえた、寄り添ってもらえたという喜びの体験がともないます。
3. 園での実践事例
東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(Cedep)の調査では、多くの園で効果的な取り組みが紹介されています。
効果的な取り組み例
環境設定の工夫 子どもたちがイメージしたことをすぐ実行できるように道具の種類を多くし、スペースの確保に努めている。必要以上に子どもに関わり過ぎないようにする。効果:子どもが自発的に行動したり、積極的に質問したりする姿が見られるようになった、子ども同士のトラブルも自分たちで解決できるようになった。
自然体験の重視 園庭に泥団子のコーナーを用意し、たくさんの木々を植えている。雨の日はカッパを着て外に出て、雨を感じる。効果:いろいろな砂の感触を感じたり、実際に雨に触って確かめたりしながら、探求していく様子が見られた。
異年齢保育の実践 学年の違う子と関わる機会を作っている。普段はおとなしい子どもをあえてリーダーにしてみる。自分を発揮する場面やきっかけを作る。効果:末っ子や一人っ子の園児も、下の学年と関わることで我慢しなければいけないことが出てくる。コントロールする力や、人と関わる力が育った。自信が持てるようになった。挑戦したいという気持ちが出てきた。
家庭でできる非認知能力の育て方
日常生活での実践
私たち編集部が実際に試してみて効果を感じた方法をいくつかご紹介します。
1. 感情の言語化を促す
子どもが感情的になったとき、「悔しかったんだね」「嬉しそうだね」と感情に名前をつけてあげることで、自分の気持ちを理解し、コントロールする力が育ちます。我が家では、感情カードを作って「今の気持ちはどれかな?」と子どもと一緒に確認する時間を作るようにしています。
2. 失敗を成長の機会として捉える
非認知能力には、自分の感情をコントロールできる力、気持ちの切り替えができる力もあります。自分の気持ちをコントロールするというのは、感情を押し殺して我慢をするということではありません。自分の思い通りにならないから、と怒ったり、泣いたり、相手のことを傷つけたり、何かをやってもうまくいかないからと途中で投げ出したりするのは、感情のまま行動している印象を与えてしまいます。
失敗したときこそ、「どうすれば次はうまくいくかな?」「何が学べたかな?」と前向きな声かけを心がけています。
3. お手伝いを通じた責任感の育成
年齢に応じたお手伝いを継続することで、責任感や達成感を育むことができます。3歳なら食器を運ぶ、4歳なら洗濯物をたたむなど、「ありがとう、助かったよ」という感謝の言葉と共に任せることが大切です。
習い事選びのポイント
非認知能力を育てる習いの選び方としては子どもが興味のあることや好きなことといったことをポイントに選ぶと良いでしょう。また、勝敗や成功失敗にこだわらずに長く続けられるものがよさそうです。
おすすめの習い事タイプ
| 習い事の種類 | 育まれる非認知能力 | 選び方のポイント |
|---|---|---|
| 音楽系(ピアノ、合唱等) | 忍耐力、表現力、協調性 | 発表会で失敗を恐れない環境か |
| スポーツ系(サッカー、水泳等) | 粘り強さ、チームワーク、自制心 | 勝敗よりも楽しさを重視しているか |
| 芸術系(絵画、工作等) | 創造性、集中力、自己表現力 | 自由な発想を認めてくれるか |
| 総合型(幼児教室等) | 多様な力をバランスよく | 様々な活動を通じて可能性を広げられるか |
編集部スタッフの体験談として、娘をピアノ教室に通わせているママからは「最初は上手に弾けなくて泣いていたが、先生が『今日はここまでできたね』と小さな成長を認めてくれることで、諦めずに続ける力がついてきた」という声がありました。
非認知能力育成で気をつけるべきポイント
1. 年齢に応じた期待値の設定
非認知能力とは物事に対する姿勢や取り組み方、他者との関係の構築など、日常生活や社会活動において重視される能力を指します。これらは主に4歳~5歳の幼児期に大きく発達し、学童期・思春期に伸びていきます。
無理に早期から高い能力を求めるのではなく、子どもの発達段階に合わせた関わりが重要です。
2. 過度な介入は避ける
子どもが、何かに夢中になっているときは、非認知能力が働いているときだといえます。子どもが物事に興味・関心を持ち、自らの意志で行動する力が発揮されている状態です。自分の意志で意欲を持って物事に取り組むとき、子どもは大人以上に集中力を高め、試行錯誤や創意工夫を積み重ねます。
子どもが集中しているときは、むやみに口出しせず見守ることも大切です。
3. 完璧を求めすぎない
非認知能力は「能力」と括られていますが、この個人の特性による能力すべてが「高ければよい」というものではないということに留意が必要です。例えば、自尊心が高すぎて自分の失敗を認めず人のせいにしてしまったり、自制心が強すぎて感情を伝えられなかったり、場合によっては負の影響が生じる可能性もあります。
バランスの取れた発達を目指すことが重要です。
非認知能力と将来の関係性
学習面での効果
非認知能力が高い子どもは、学習に向かう姿勢そのものが異なります。困難な問題に直面しても諦めずに取り組む力、友達と協力して学習する力、自分の学習をコントロールする力などが身についているため、結果的に学習成果も向上する傾向があります。
社会生活での効果
将来的には以下のような効果が期待できます:
- 職場での人間関係構築力
- リーダーシップ能力
- ストレス耐性
- 創造的問題解決能力
- 継続力と責任感
編集部で働くスタッフたちも、「幼少期に培った『最後までやり抜く力』が今の仕事でも活かされている」「人との関わり方を学んだ経験が、チームワークの向上に役立っている」といった実感を持っています。
まとめ:非認知能力育成のための親の心構え
非認知能力は、子どもの人生を豊かにするための土台となる力です。しかし、一朝一夕で身につくものではありません。日々の生活の中で、子どもの「やってみたい」「知りたい」という気持ちを大切にし、失敗も含めて様々な体験をさせてあげることが重要です。
保護者として大切にしたい3つのポイント
- 子どもの興味・関心を尊重する 子ども自身が「やりたい」と思うことを大切にし、それを支援する環境を整える
- プロセスを認める 結果だけでなく、努力や工夫した過程を認めて言葉にしてあげる
- 応答的な関わりを心がける 子どもの発信に対して適切に応答し、安心できる関係性を築く
非認知能力の育成は、特別な教材や方法が必要なわけではありません。日々の生活の中で、子どもと向き合い、共に成長していく過程そのものが、最も効果的な教育となります。
我が子の将来を思うご夫婦の愛情こそが、非認知能力を育む最高の環境なのです。子どもの可能性を信じ、長い目で見守りながら、一緒に歩んでいきましょう。